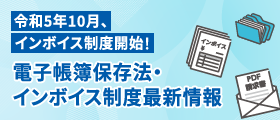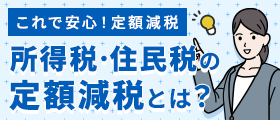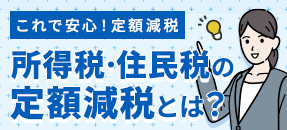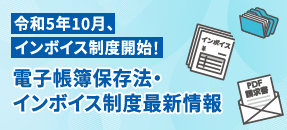当サイトでは、Google社のボット排除サービス「reCAPTCHA」、アクセス解析サービス「Googleアナリティクス」を利用しています。
■ reCAPTCHAの利用について
当サイトのお問合せフォームでは、ボットによるスパム行為からサイトを守るために、Google社のボット排除サービスであるreCAPTCHAを利用しています。reCAPTCHAは、お問合せフォームに入力したデバイスのIPアドレスや識別子(ID)、ネットワーク情報などをGoogleへ送信し、お問合せフォームへの入力者が人間かボットかを判定します。
reCAPTCHAにより収集、記録される情報には、特定の個人を識別する情報は一切含まれません。また、それらの情報は、Google社により同社のプライバシーポリシーに基づいて管理されます。お問合せフォームへの入力は、Googleのデータ収集に同意したものとみなされます。
■ Googleアナリティクスの利用について
当サイトでは、お客様の当サイトへのアクセス状況を把握するために、Google社のアクセス解析サービスであるGoogleアナリティクスを利用しています。Googleアナリティクスでは、当サイトが発行するクッキーをもとにして、Google社がお客様のアクセス状況を収集、記録します。当事務所は、Google社からその集計結果を受け取り、本サイトのアクセス状況を把握、分析します。
Googleアナリティクスにより収集、記録される情報には、特定の個人を識別する情報は一切含まれません。また、それらの情報は、Google社により同社のプライバシーポリシーに基づいて管理されます。当サイトの閲覧は、Googleのデータ収集に同意したものとみなされます。
お客様は、ブラウザのアドオン設定でGoogleアナリティクスを無効にすることにより、当事務所のGoogleアナリティクス利用によるお客様のアクセス状況の収集を停止できます。Googleアナリティクスの無効設定は、Google社によるオプトアウトアドオンのダウンロードページで「Googleアナリティクスオプトアウトアドオン」をダウンロードおよびインストールし、ブラウザのアドオン設定を変更することで設定できます。
なお、お客様がGoogleアナリティクスを無効設定した場合、お客様が訪問する当サイト以外のウェブサイトでもGoogleアナリティクスが無効になります。その場合、ブラウザのアドオンを再設定することにより、再度Googleアナリティクスを有効にすることができます。